*【節用集】の偽版
*意次 日光社参を受け入れる
今回はこの2本建です
吉原では この頃「金々」と呼ばれ通を気取って疫病本多髷や着物の裾を長くした当世風を気取った輩が大発生
聞きかじりで通を気取り、目計頭巾((めばかり)当時は禁止されていた)を被り 半可通を気取る「金々野郎」が頻繁に現れていた
ここで『金々先生栄花夢』を連想
鱗形屋と蔦重が、青本を面白くするための話をしている「源四郎(店の金をチョロまかす悪い手代 の代名詞)」「うがち」「地口」を入れたら 面白い
占め子の兎[しめこのうさぎ](物事がうまく運ぶこと)と 蔦重
ここでは、名前が出ませんでしたが、『金々先生栄花夢』恋川春町作・画 安政4年鱗形屋出版
そして、鱗形屋が節用集偽版で捕まる前に 『金々先生栄花夢』は鱗形屋から出版され大ヒットしていたようです(蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者 松本寛 日本経済新聞社 p.28)
ドラマ上では、まだ発売されていない様子です これからこの面白い青本が発売されるのでしょう
鱗形屋【節用集】の偽版
鱗形屋の番頭と話をする蔦重 迷惑火事(明和9火事)で、店や蔵まで建て替え 板木も消失 資金繰りは厳しかった様子、息子が持っていた「節用集」が偽版と同じものか?と気づく
節用集とは
節用集(せつようしゅう、せっちょうしゅう)は、室町時代から昭和初期にかけて出版された日本の用字集・国語辞典の一種。漢字熟語を多数収録して読み仮名をつける形式となっている。
wikiより
上方文化と江戸文化が交錯する”熱田”で見つかった 「早引節用集」の偽版
そもそも「節用集」というのは、室町時代からある、国語辞典のようなもの、それを 勝手に無断で名前を変えて 出版しちゃった 鱗型屋 信用は地に落ちます
鱗形屋で「おいそぎ おいそぎ」と便所に駆け込み、おとし紙が 偽版のものと確信
西村屋と鱗形屋の話「蔦重を飼い慣らせている」と聞き、須原屋に向かうが、言い出せず つげ口できず 運を天にまかすと お稲荷さんに話す
長谷川平蔵が鱗形屋に現れ「偽版〜」と声を上げ、鱗形屋はお縄になる 蔦重も連呼されそうになるが、平蔵が、吉原のものだと言い、難を逃れる。
そのために、鱗形屋は蔦重が奉行所に密告したのだろうと、誤解する。
その後、蔦重と平蔵の会話
蔦重は偽版のことも、柏屋が騒いでいることも知っていたが、言わなかった 心のどこかで こいつが欠ければと思っていた
うまくやった うまくやることは こたえるもの
濡れ手で粟➕棚からぼた餅 濡れ手の粟餅
意次 日光社参を受け入れる
松本秀持が、倹約指導により、明和の大火(目黒行人坂大火)以前の状態まで幕府財政を立て直すことができたと報告(松本秀持は田沼意次に認められ、天守番から勘定奉行になる 後の蝦夷地開発に関わる)
白眉毛(意次らが呼んでました)筆頭老中松平武元が日光社参を執り行いたいと 上様に進言してほしいと意次に頼む、側用人兼務の意次は家治に話をしなければならなかった
ようやく財政を立て直したのに、日光社参(徳川家 旗本・譜代大名が連なって日光まで墓参りに行く、膨大な費用が必要
財政面から家治を説得するも 家治は翌年 先代家重の17回忌であり、嫡男家基も望んでいると聞き入れてもらえない そして家基が将軍になることを見据え、社参に同意することになる。
どうも、大奥や、家基の生母”お知保の方”(反田沼)が関わっていそう
日光社参が決まると、白眉毛が意次に
「馬には乗れるのか?」
「馬や武具は?」
「兜はどこであつらえるか、ご存知か?」と・・・
意次
「高家吉良さまよろしく 御指南ください」と
佐野善左衛門政言も登場しました
田沼意知と佐野善左衛門政言の会話
佐野家系図 田沼家は佐野家の末端の家臣だった それを改竄しても良いから出世させて欲しいと言ってきた。
意次は由緒など どうでも良いと 系図を池に投げ入れてしまった
これはその後 意知の殿中沙汰に繋がる 池に落としちゃったんだから 返せないよな〜
小島藩が出てきました これよくわからない
社参取りやめのお願いに キラキラ山吹(小判)を入れて、松本秀持に渡す
家臣が偽版に関わったと判明した時は、当家が関わり無しとして欲しいと
小島家と鱗方屋が関わり合いがありなのか?
恋川春町は小島家家臣だよなあ (春町の死因に関係するのか?)
今回も情報盛りだくさんでございました どう展開していくのでしょうか
朋誠堂喜三二どこに登場していたのか、わかりましたか?
そして、意次の側近 三浦庄司 (役・原田泰造)オープニングロールで良い位置にいるんだけれど、重要な役割を果たすのでしょうか
楽しみです


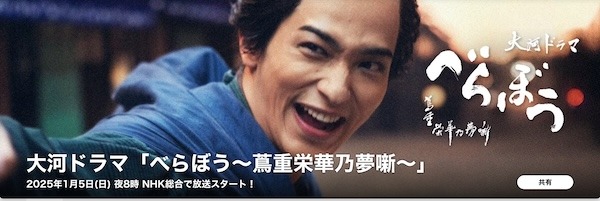
コメントを残す