本間さまの話を聞いて、上杉鷹山との関連もあったと・・・
家にある「上杉鷹山」童門冬二を再読した。

本間様との関連はこの本には、名前だけしか出てこなかったけれど、上杉鷹山やっぱり凄し
以前に読んだけれど再読すると余計にわかるのが不思議
日向高鍋藩から米沢藩主上杉家に養子に入り17歳で藩主になる。
その後米沢藩の財政立て直し藩政改革を断行する。
米沢藩は吉良上野介の息子を養子に迎え、公家筆頭の吉良家との縁、武家としての最高の格式を示さねばならなかった、かつて120万石が30万石に減らされても藩士を削らなかった。
財政逼迫は、物語最初に、誰も米沢藩に金を貸してくれないことから始まる。
上杉家重臣たちは、すでに藩財政が逼迫している時期に、治憲(鷹山)の改革に反対、阻止しようとする。
重臣達の抵抗を予測していた治憲は、藩の体制からはみ出している者たちを集めて改革案を練らせる。
「改革は城のためでなく、民〈たみ〉のためにおこなう」が根底にある。
はみ出し者たちが、藩政を仕切っていく、旧守派重臣たちは抵抗する。
それぞれが、自分たちが正しいと信じる。
田沼時代、治憲の改革が受け入れられるには、困難の多い時代だったであろう。
今まで通りの、重臣たちの政治、事なかれ主義の武士対面を尊重する面々
武士でも庭に漆・楮・桑 紅花・藍を植え 妻は機を織る 鯉を飼うを奨励
治憲、自ら着衣は木綿、食事は一汁一菜を基本としていた。
士農工商を覆すと重臣たちは抵抗する。
当時藩は人民の合意の合意を実行する機関であるという、民主主義の思想は受け入れられないのは当然だったのかもしれない
本当に、20歳前後の人物だろうか?と思われる様な発言や、執政
それでも、これだけの改革をやってのけたのは、若い力があったからなのかもしれない。
「藩政改革は、藩民のためにおこなうものだ」
治憲の改革の根底には「領民と藩士への限りない愛情があった」
倹約一辺倒でなく、「生きた金」を「領民を富ませるために」惜しみなく使う気でいた。
細井平洲を招いて学校を作る。
武士も商人も農民も通える学校を作る。
重臣たちの抵抗を治憲たち改革派は少しづつも、改革に成功していく
この先、まだいろいろあるのですけれどね
さて、今の菅政権の政治を見ていて、
もしも 鷹山がコロナ対策を含め現在の政治を改革するとしたらどうするか???
城(一部の人)のためでなく、領民(国民)のために、愛情を注ぎつつ、政治を行っているだろうか???
コロナ対策を軽視していないか?
gotoトラベルをなかなか中止しなかった。
国民には自粛をせよといいながら、連日のハシゴ会食する菅首相
それも、政治をおこなう手段だったら、愛情を持って国民に説明をお願いしたい。
自民党公明党の議員の皆様に考えていただきたい。
菅首相、ご自分の政治が正しいのか?国民のために行われているか?考えてほしい。
上杉鷹山の化身が現れないか???


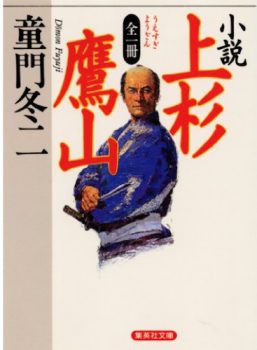
コメントを残す