べらぼうで ケン・ワタナベが演じる 田沼意次
田沼時代の政治に興味があって これを読んでます

恐ろしいほどの権力を持った田沼意次が細かく書かれています。
江戸仲間からの「なぜ 意次は賢丸(松平定信)を無理クリ白河藩に養子に出したのか?次の将軍予定の豊千代の父 治済とどういう関係なのか?」を知りたいと思って読み始めました。
田沼意次は賄賂政治として歴史では習ってきたけれど、近年では違う見方がされているらしい
賄賂汚職と悪政の代名詞であった田沼意次は、老中を辞職した後、意次が失脚したあと吹き出したさまざまな悪評が作り出したものであり、積極的経済・財政政策 政治的手腕 度胸のある大政治家だった
家重の小姓として支えてから 側用人の役のまま老中になり 大大名に そして没落
田沼時代の全盛期は老中は皆縁戚関係にあり幕閣は意次に引き立てられたもので固められ、大奥までも意次の妾関連から力を伸ばしていた、意次自ら取り込んだ者もいれば、取り込んでもらおうと近づくものも大勢あった
ドラマ「べらぼう」で描かれているケン・ワタナベ 頂点に登りつつあります。意次はただただ賄賂政治だけじゃなく描かれそうです 背景には上方文化から独立して江戸文化に花が咲き 商業の発達 利を追求する「山師」の存在 (これは、鉱山開発の山師だけを指すのではななく)
今 読んでいるところに面白い記述があったので紹介
意次が 利益追求型の政治を行い「山師」は悪であったのか?という所
興利については、新井白石 荻生徂徠の説明もあり
そもそも 武士にとっては興利(利益を求めること)はハシタナイことであり、儒者にとっても同じ、しかし新井白石や荻生徂徠は儒学者として、書物の上ではなく、現実の社会を直視していたと
海保青陵の文 引用
海保青陵は、興利にも上手と下手の二つがあるという。「興利ニ2種アリ、真ノ興利ハ周来ノ法也、呉王濞(ビ)ノシワザ也、下手興利ハ民ノ喉ヲシメテ、無理ヤリ民ヨリ金ヲトル也、コレハ興利ト云モノニハナシ、虐民トイフモノ也、呉王ハ民ヲバ作リ取リニサセテ、金ヲウントタメタルハ興利ノ上手也」(『日本思想大系 本多利明・海保青陵』p.244)と書く。上手の興利、真の興利だという『周礼』の法、呉王のやり方は、まず民間を豊にさせて金を蓄えさせ、その後に国が民間から利を吸い上げる。という手法で、下手の興利は、民間の首を締めて無理矢理に金を搾り取る、というやり方らしい。田沼時代を特徴づける「興利」策は、海保青陵の基準からすると、上手だったのか下手だったのか。
『田沼意次』藤田覚 ミネルヴァ書房 p.84
国会が開かれています
現代にも通じる文章であります


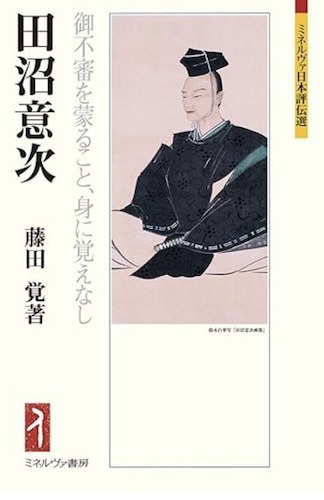
コメントを残す